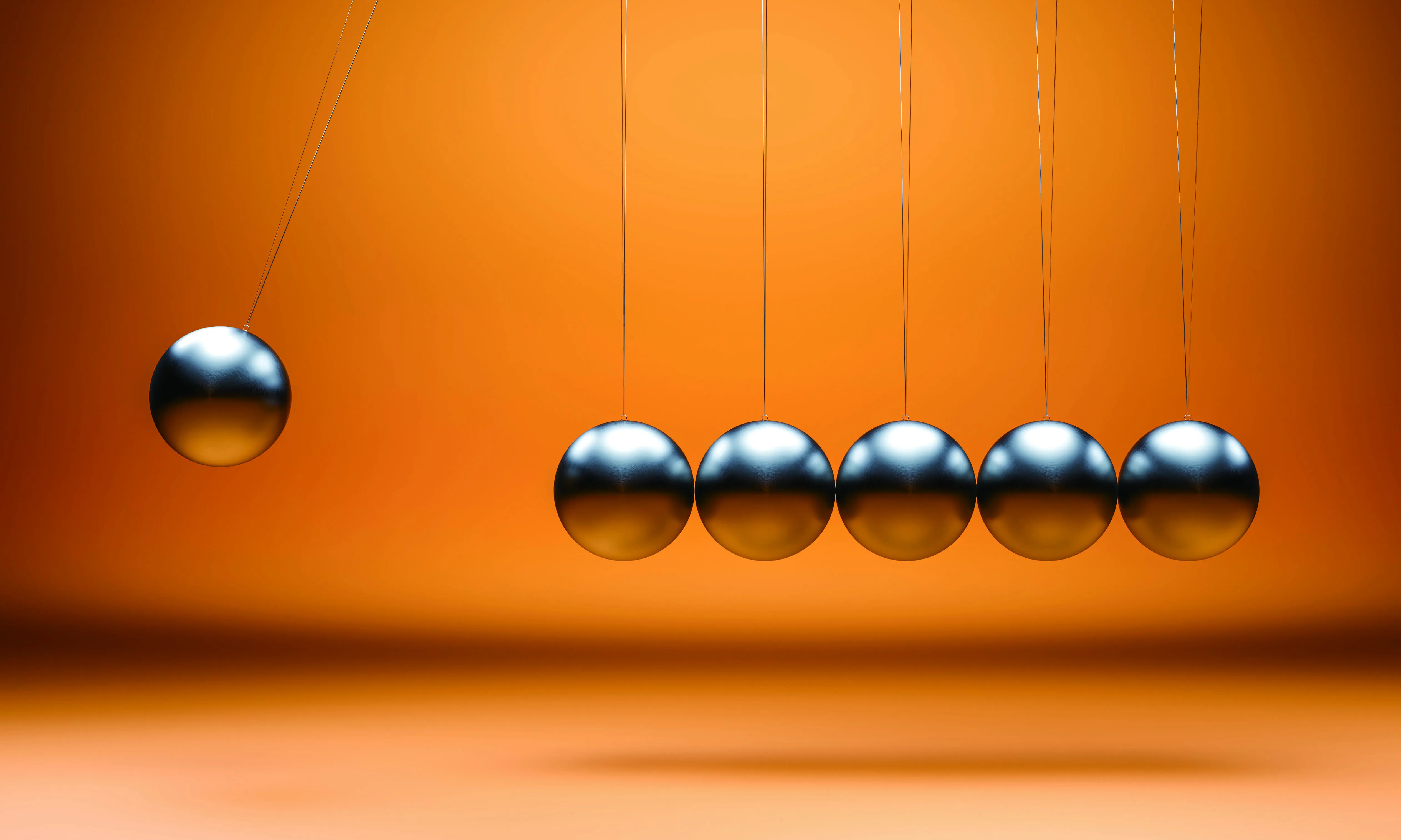◆オルタナ56号 連載「論考・サーキュラーエコノミ」から
私ごとで恐縮だが、私の生まれは昭和28年(1953年)、日本経済が高度経済成長期に入ろうかという頃で、戦争の混乱は急速に収束しつつあった。それでも、幼い頃の記憶に戦争の傷跡らしきものが残っている。度々傷痍軍人の姿を見かけることがあり、ヤミ市もどきの新宿駅界隈の雑踏も頭のどこかにこびりついている。
食べるものも質素だった。流石に戦中や終戦直後のような飢えは経験せずに済んだが、ご馳走にありつくことは滅多になかった。子どもの頃、刺身などほとんど口にしたことはないし、時たま食べるすき焼き(これはご馳走だ!)の肉は豚肉だった。私は成人になるまですき焼きの肉は豚肉と固く信じていて、あるとき事実を知って顔を赤くした記憶がある。
ところが気が付かないうちに「飽食の時代」と言われる時代が訪れ、日本人の間にもグルメが当たり前のこととなった。もちろん食の楽しみは人生にとって大切なことで、グルメ自体が悪いということではない。だが、食べられるにもかかわらず余ったものは平気で捨ててしまうということになったらそれは問題だろう。しかしそれは実際に起きているのだ。
農林水産省の推計によると、2015年度の食品廃棄物の量は2842万トン、食べられるのに捨てられてしまう食品、すなわち食品ロスの量は646万トンである。昔の感覚でいうと「まだ食べられる」食品も食品廃棄物の中に含まれているに違いないから、もったいない話である。




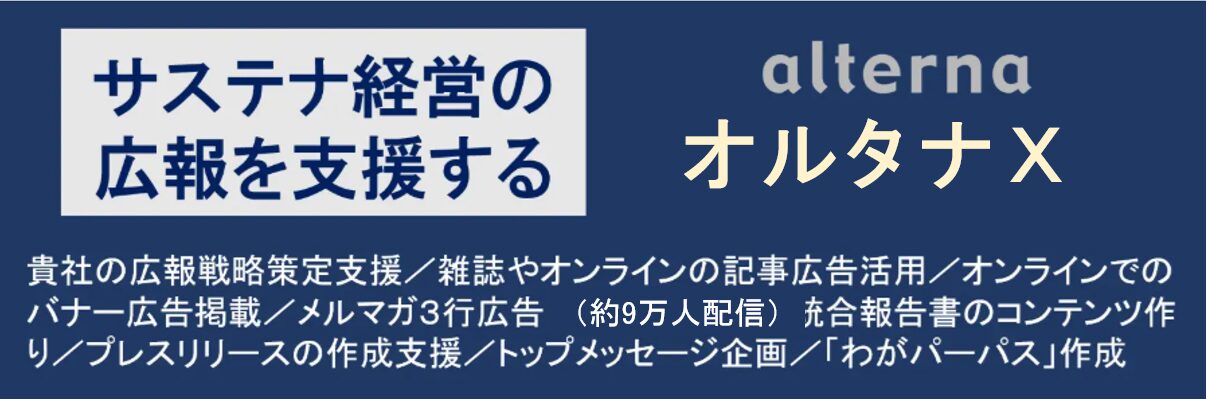
























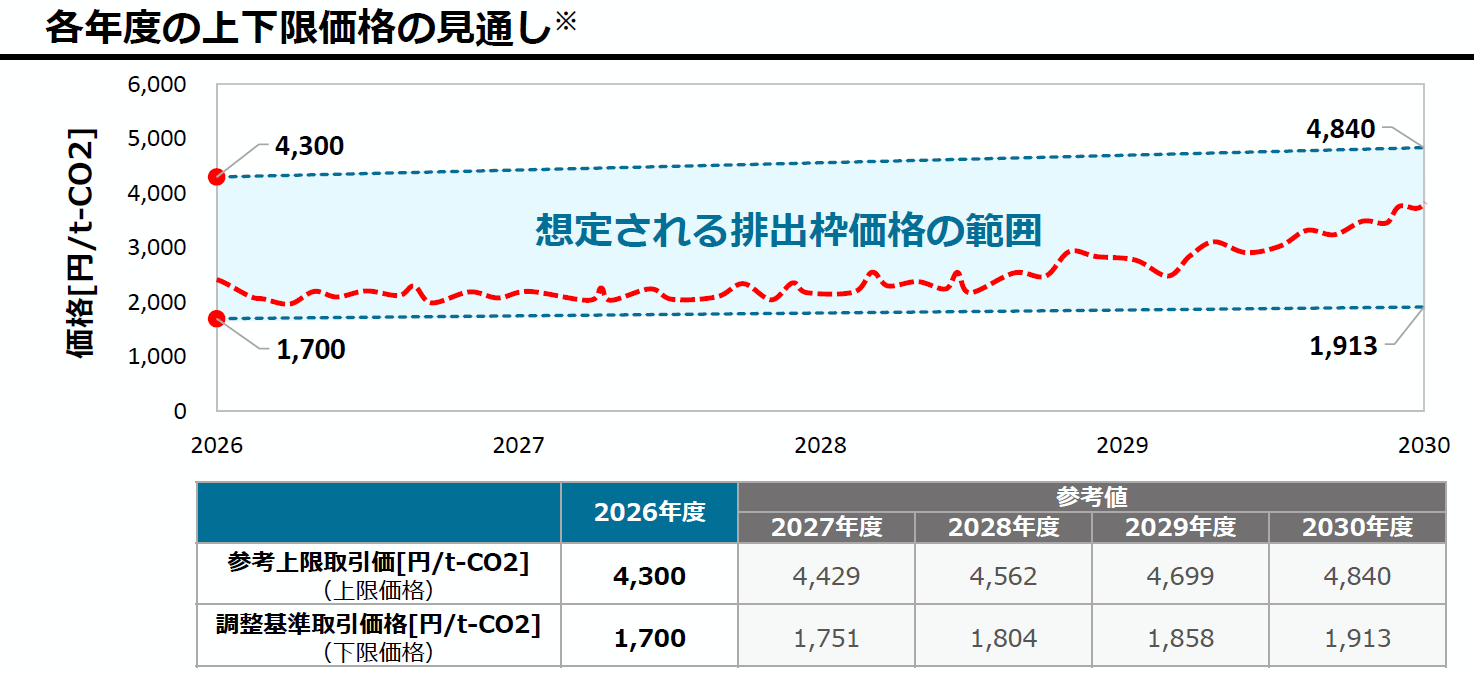
.jpg)