日本でも企業の戦略や業績などの「財務報告」と、ESGやCSRなどの「非財務報告」が一体となって企業の価値を表現する「統合報告」の発行が年々増えています。昨今の国内の統合報告の趨勢を見ている中で、少し投資家向けに重心が置かれ過ぎ、ESG情報は財務的成果に結びつかなくては意味がない、と断じられている傾向にやや疑問を感じている今日この頃です。私自身、まだ答えのない旅の途中ですが、ここにひとつ別の見方を提示してみたいと思います。今回は、この問いに対応するように変化している「コーポレート・ガバナンス」について考えてみたいと思います。
■コーポレート・ガバナンスにおける二元論
コーポレート・ガバナンスとは、「企業は誰のものか」という命題をベースに、企業の所有者が企業経営を監視していくためのシステム(体制)のことですが、大きくドイツなどに見られる「企業はステークホルダーのもの」というステークホルダー型と、米国などで典型的な「企業は株主のものである」という株主型の2つの流れがあり、日本では従来より実質的には従業員を中心としたステークホルダー型であると言われてきました。
しかし、特に日本における外国人株主の増加に伴い、昨今のコーポレート・ガバナンス改革の旗のもと、これまで劣位に置かれてきた株主の権利を強化する方向に舵が切られています。
日本において統合報告が投資家寄りになっている理由のひとつに、このコーポレート・ガバナンスの概念が「株主のためのガバナンス」に近づいている側面も大きいのではないかと考えられます。
コーポレートガバナンス・コードには5つある原則の2つめに「ステークホルダーとの協働」と明記されていますが、ステークホルダーエンゲージメントやES側面の意思決定をコーポレート・ガバナンス(指名・報酬・監査等)に組み入れている企業は希です。
ESG要因を、企業価値・財務パフォーマンスに結びつける方法の模索がなされている『企業価値分析における ESG 要因』 日本証券アナリスト協会(2010年)は、アナリストの目線でのレポートですが、マルチステークホルダーの観点も忘れずに以下のような記述も見られます。




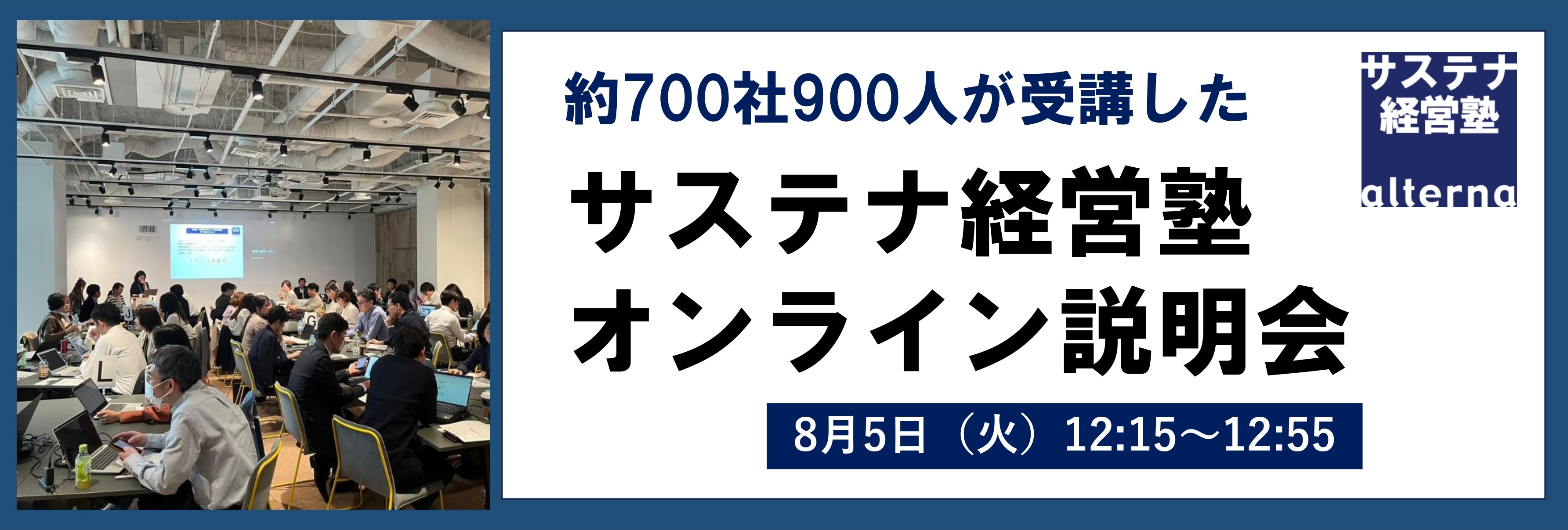




-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)























