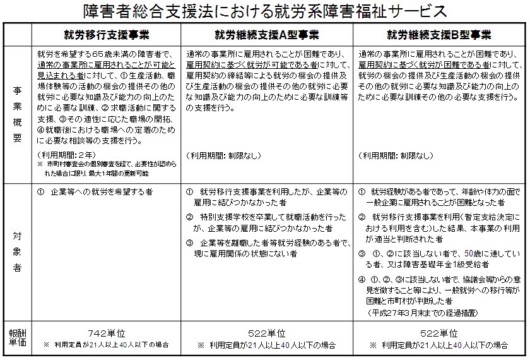
また、就労支援事業所は公的なサービスとして一般就労に向けての支援も行う役割があり、就労を希望する障がいのある人と、雇用を検討する企業との細かな調整をしながらジョブマッチングを図るプロセス(第1回コラム「障がい者雇用成功のカギは採用プロセス」参照)があるが、事業所に通っても就職活動は障がいのある人が自力で行っているというところもある。
もちろん、事業として成り立たせていくためには、ビジネスとして確立する必要があるが、収益性や将来性に加えて、利用者にとってやりがいのある作業であることや障がい特性に合わせた職務構築であることなども重要な視点となる。
さらに、公金が活用されている事業であるため、事業所のための事業ではなく、障がいのある人の社会参加を促すための支援体制を、地域社会のあらゆる資源と連携しながらネットワークを構築していくというソーシャルワークが事業のベースであり、「地域にどのような社会ニーズがあるか」というのが事業立ち上げに最も重要な視点の一つである。
地域ごとの社会ニーズは様々であるが、それぞれのニーズに沿った受け皿として継続的に機能していける事業所が増えていくこと願いたい。
では、利用者及び関係者にとっての事業所の見分け方についてどのような方法が考えられるのだろうか?
次回のコラムでは、事業所の選び方について説明していきたい。




























.jpg)





