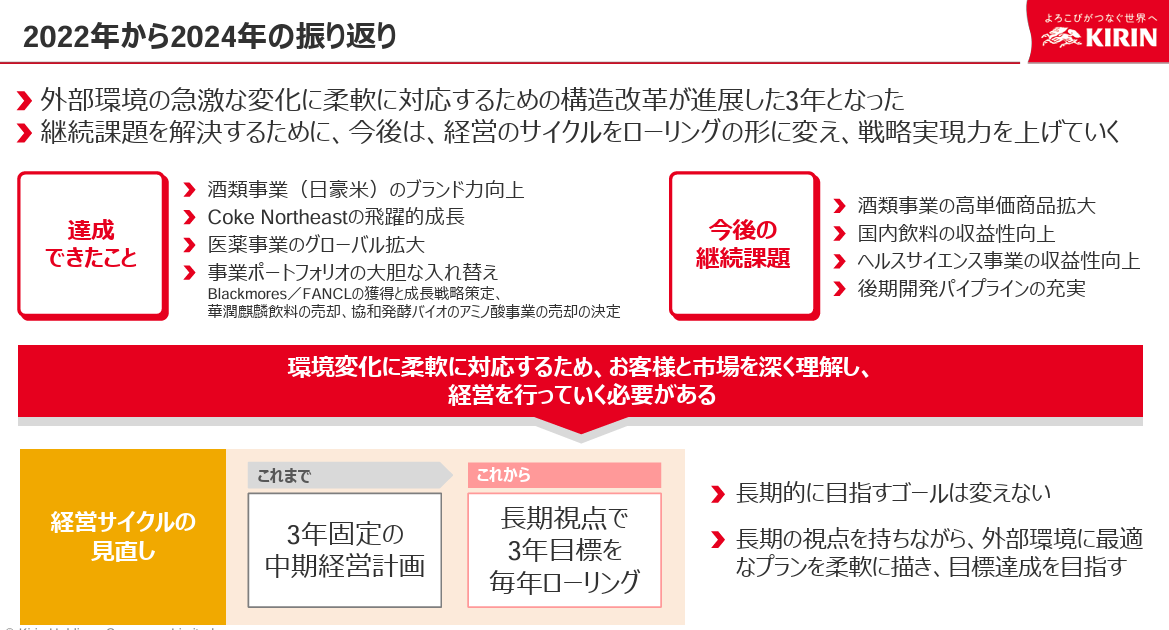価値創造のルーツは数千年前にあった
日本有数の山脈に囲まれた雪深い山国として、かつては外界と途絶されていた飛騨地方。だからこそ、独自の価値・文化が発達したものと長年考えていました。しかし、改めて調べていくうちにそれは私の浅知恵だと気づきました。
調べてわかったことは、実は縄文中期という太古の昔から北陸や信州との文化的な交流が確認されていたことでした。そうしたことから、飛騨地方には良い木材資源にめぐまれ、北陸方面から得た技術もあいまって製材・木工についての特殊な技術を習得した人々がいたことが早くから中央政府に認識されていたというのです。
縄文中期というと約三千年~五千年前です。この時期から飛騨のオープンな外部との交流がなければ、木工の発展、すなわち今の高山の発展はなかったと考えられます。
その外部との交流が結実していくのは4世紀、漢の建築技術を伝える「てひと」を迎え、その木工技術を吸収していくことになります。それが高い匠(たくみ)の技に発展してくことになったと思われます。ここでも、飛騨人(ひだびと)たちは、外から技術を学んだことが分かります。
この「匠」が歴史に刻まれる形で認識されたのが奈良時代です。雪国で貧しかった飛騨地方は、中央政府への税を払うことができませんでした。そこで税を免除される代わりに、匠丁すなわち宮大工を出すことになります。
金(米)を払えないから体で払う、いえ、金を払えないから技で払う、これが飛騨人の凄さであります。価値と価値の交換です。このとき宮大工として仕えたのが、今でいう「飛騨の匠」と呼ばれる人々です。万葉集にも登場した飛騨の匠たちは、平城京の西隆寺、正倉院の宝物など数々の重要な仕事に関わりました。
伝説の怪物「両面宿儺(りょうめんすくな)」