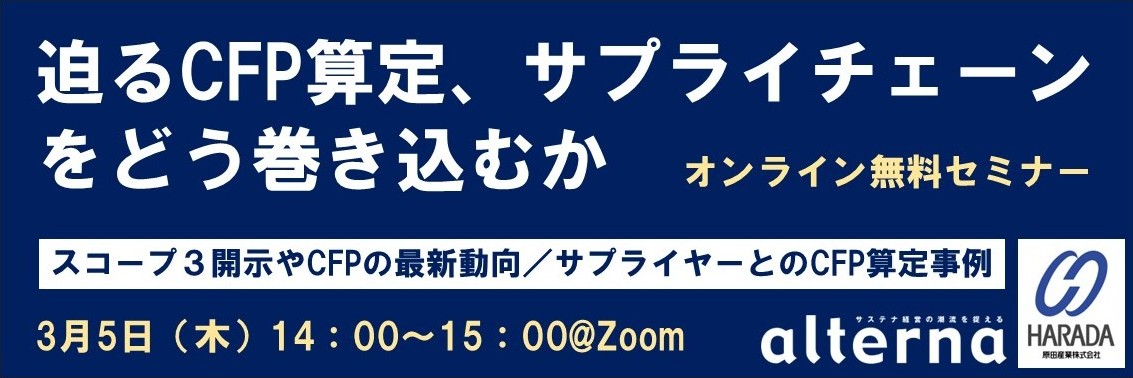■トップインタビュー
坂本龍一さんが3月28日、逝去されました。71歳でした。 坂本さんは音楽や芸術だけでなく、自然、地域の在り方、平和、脱原発などにも大いに取り組み、自ら数多くの地域に足を運ばれました。2007年には、森林保全活動を行う一般社団法人「more trees(モア・トゥリーズ)」を立ち上げ、地域の活性化にも力を注がれました。オルタナ本誌56号(2019年3月発売)に掲載したインタビューを再掲します。
◆
世界的な音楽家、坂本龍一氏は2007年、森林保全活動を行う非営利団体「more trees(モア・トゥリーズ)」(東京・渋谷)を立ち上げた。東日本大震災の被災地や福島の避難区域、石木ダム計画の建設予定地(長崎県)などにも足を運ぶ。こうした社会的活動に取り組み続けて達した結論は「人間も企業も『反自然的な存在』。だからこそ自覚を持つべきだ」と話す。その真意を聞いた。(聞き手: 森 摂=オルタナ編集長、吉田 広子=同副編集長、写真:福地 波宇郎)
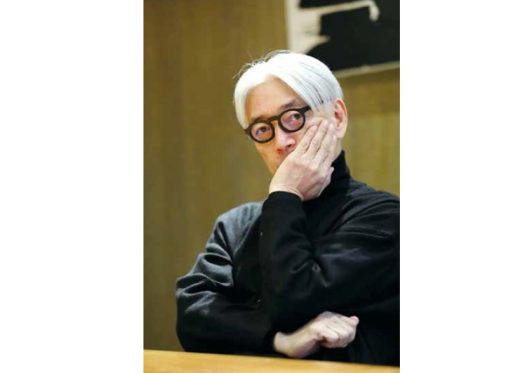
――坂本さんはそもそもサステナビリティ(持続可能性)をどのように考えていますか。
まず、現代の人間は長生きし過ぎだと思います。両親は2人とも他界しましたが、1人の人間が死ぬと、膨大な物が残ります。とにかく物が多い。1人の人間が生きている間、莫大な消費があり、それだけでも環境に大変な負荷がかかっています。
1万2千年くらい前までは地球全体で総人口が恒常的に500万人ぐらいといわれ、30人から50人くらいのコミュニティーで生きていたそうです。環境に守られつつ、自然の恵みを受けて、あまり環境に負担のかからない生き方をしていました。
ところが、この100年で人類は急速に資源に依存し、環境への負荷が指数的にものすごく上がりました。
■100年で急速な変化
――世界人口は現在75億人でこの50年で2倍になり、2050年には98億人に達すると見込まれます。
特に、日本や米国、欧州などの先進国では、長生きが顕著です。100年前の日本では、人生50年と言われたものです。今では日本人の平均寿命は80歳を超えています。
――これからは人生100年時代だと言われています。
「アンチエイジング」など、正直いかがなものかと思います。個人のサステナビリティは、短い方が良いです。コミュニティーや地球全体のサステナビリティを実現するためには、個人があまりに負荷をかけ過ぎていますから。
決して「人間はいなくなった方が良い」と言っているわけではありません。生きているだけで、どれだけ負荷をかけているのかを、人間は自覚するべきです。「寿命を延ばせば良い」というだけの考えは、おかしいと思います。
――サッカーの元日本代表監督の岡田武史さんも、オルタナとのインタビューで「『地球を守ろう』と言うのはおこがましい。むしろ存続が危ないのは人間だ」と話していました。
地球の寿命はあと50億年と言われています。人間が「地球を守れ、自然環境を守れ」というのは、まぁごう慢ですよね。自分たちで壊しておいて自分で守れと言っている。
動物はそんなことはしません。与えられた自然環境の中で、増えたり減ったりしている。天敵がいなくなれば個体数は増えますが、そうすると自分たちの首を絞めるので自然淘汰されていきます。
自然の恩恵を受けて生きているのに、人間は自然環境を自分たちの技術力で大きく変えてしまいました。だからこそ「人間は反自然的な存在」だと自覚しなければ。
――日本人は昔から環境意識が高いと言われますが、気候変動対策や「海洋プラスチック憲章」に署名しないなど、遅れている面もあります。
日本人の意識が高いというよりも、「言われたから」あるいは「隣がやっているから」ということも大きいのでは。日本人の集団心理はよく批判されますし、僕も集団圧力の強い社会だと感じることもあります。
しかし、自分たちの環境を守ることにおいて、プラスに作用しますね。「みんながやっているから、自分だけやらないわけにはいかない」といった集団心理で動くことも意味があるからです。
■顕著な気候変動の影響

――2018年も気候変動の影響が顕著でした。米国でも大きなハリケーンが何度も襲来しましたね。
僕はニューヨークに住んでいますが、ブルックリン地区でも竜巻が起こりました。日本も12月だというのに、20度を超えた日もあります。
ですが、ニュース番組を見ていても、人々はあまり危機感を感じていないように見える。視聴者が危機感を感じないようにわざと演出しているかな。「暖かくて良かったね」なんて言っているのは、とんでもないと思うのですが。
――テレビの気象情報でも、「気候変動」や「地球温暖化」という言葉はあまり使いません。
「地球温暖化の影響、かもしれない」といった曖昧な表現にしている。あれはやはりお上の指示なんですかね。
――米国でも地球温暖化に対する懐疑論は根強いですね。トランプ大統領がその筆頭で、パリ協定から離脱することを宣言しました。
巨大な力を持つ石炭・石油関連企業が、膨大なお金を使って、全米の隅々の学校までそうした教育をしているようです。たくさんの科学者も買収され、懐疑論に合わせるような論文を書いたり言ったりするんですね。
――一方で、米国が健全だと思えたことの一つは、トランプ大統領がパリ協定離脱を宣言したとき、「We are still in」(われわれはパリ協定にとどまる)という動きが生まれました。
民間企業や大学、カリフォルニア州知事やニューヨーク州知事が加わりましたね。大統領が「パリ協定から抜ける」と言っても関係ない、もっと団結してやるんだと。
――そこはすごく健全だと思いました。例えば日本では安倍首相が何かを言って、それに対して、自治体や企業が反対意見を言うことはほとんどないわけです。
知事レベルになると難しいでしょうね。しかし、本当にコミュニティーから選ばれた市長や町長といった人たちは、意見を言っていることが多いと思います。実際にお会いすると、僕なんかよりもきつい事を言っている人もいますよ。
モア・トゥリーズの活動で、全国各地の町長や市長とお会いしますが、一緒に飲んだりするととても意識が高い人が多いことを実感します。
■見えない放射能の恐さ
――沖縄の辺野古の問題を巡っても、中央政府と地方自治体の首長との対立もあります。いずれにしても、環境問題も含めて、何が起きているか一人ひとりがしっかり見極めて、言いたいことが言える社会にすることが重要です。日本の民主主義は今、揺らいでいるのではないでしょうか。
地震が急にグラっとくるのに比べて、気候変動は変化が緩やかです。ですから、のらりくらりしているわけです。残念ながら、100人が100人とも行動を起こすのは難しいでしょうね。
もっと分かりにくいのは、放射能の被害でしょう。見えないし臭わない。センサーがなければ人間の感覚で受け止められない。僕も2011年の夏に福島に行きましたし、その後も何度か足を運んでいます。
行った方は分かると思うのですが、非常に美しい田園風景が広がっています。福島第一原発のすぐ近くにも田園風景が広がっている。センサーさえ持っていなければ、本当にのどかな日本の田舎です。しかし、センサーで測ると針が振り切れてしまった。それで慌てて引き返してきたのですが、体感としては何も感じないわけです。
ですから、原子力村は良いものを見つけて稼ぎにしているなと思いました。しかも除染した土を日本中にまいてしまえば、病気になっても因果関係が分からない。もう、とんでもない状況だと思いますが、原子力という利権をなかなか手放したくないというのは、仕方がないのかもしれません。
坂本龍一(さかもと りゅういち)
1952年、東京生まれ。東京芸術大学大学院修士課程修了。1978年『千のナイフ』でソロデビュー。同年、細野晴臣、高橋幸宏と「YMO」を結成、1983年に散開。出演し音楽を手がけた映画『戦場のメリークリスマス』(1983年)で英国アカデミー賞音楽賞を、『ラストエンペラー』(1987年)でアカデミー賞作曲賞、ゴールデングローブ賞最優秀作曲賞、グラミー賞映画・テレビ音楽賞を受賞。その他、受賞多数。1999年制作のオペラ『LIFE』以降、環境・平和活動に関わることも多く、論考集『非戦』の監修、森林保全を推進する「more trees」の設立など、活動は多岐にわたっている。