■オルタナ本誌60号 FEATURE STORYから
PETボトルの年間総販売量が252億本(2018年)にまで増えたなか、省庁や自治体では急速に脱PETボトルが進む。背景には、容器包装リサイクル法の下でのメーカーのコスト負担が全体の1.6%と少なく、回収コストのほとんどを自治体が負担している現状がある。(オルタナ編集委員・栗岡 理子)
市役所からPETを一掃

多くの自治体が最近、これまでとは違った形で、脱PETボトル化を鮮明にし始めた。その手法は以前より具体的で徹底している。マイカップ対応自動販売機やウォーターサーバー設置など、代替策も分かりやすく、実行されやすい。
神奈川県鎌倉市は2018年10月、「かまくらプラごみゼロ宣言」を発表した。これによりPETボトル飲料を会議で使用しないことを徹底した。職員のマイボトル使用も徹底した。市役所内を見渡すと多くの職員の机の上にマイボトルはあるが、PETボトルは見当たらない。
庁舎の自販機はもちろん、他の市関連施設の自販機からもPETボトルを排除した。売店にもPETボトル入り飲料を置かない徹底ぶりだ。市役所1階に置いた無料の給茶機で、湯飲み茶碗でお茶を自由に飲める。売店のある4階には、マイカップ対応の自販機も置いた。
鎌倉市のこの徹底ぶりの背景には、従来から提唱している「ゼロ・ウェイストかまくら」の理念がある。ごみ削減に徹底的に取り組み、リサイクル率は51.5%(2017年度)と人口10万人以上50万人未満の市の中では全国2位の高さだ。
焼却炉も2024年度末には稼働を停止する。同市の脱プラは、このゼロ・ウェイスト政策、さらにはサーキュラーエコノミーへの移行の一環として行われている。
*この続きは雑誌「オルタナ」60号(第一特集「循環経済(サーキュラーエコノミー)はR(リサイクル)よりもR(リデュース)」、3月30日発売)に掲載しています。




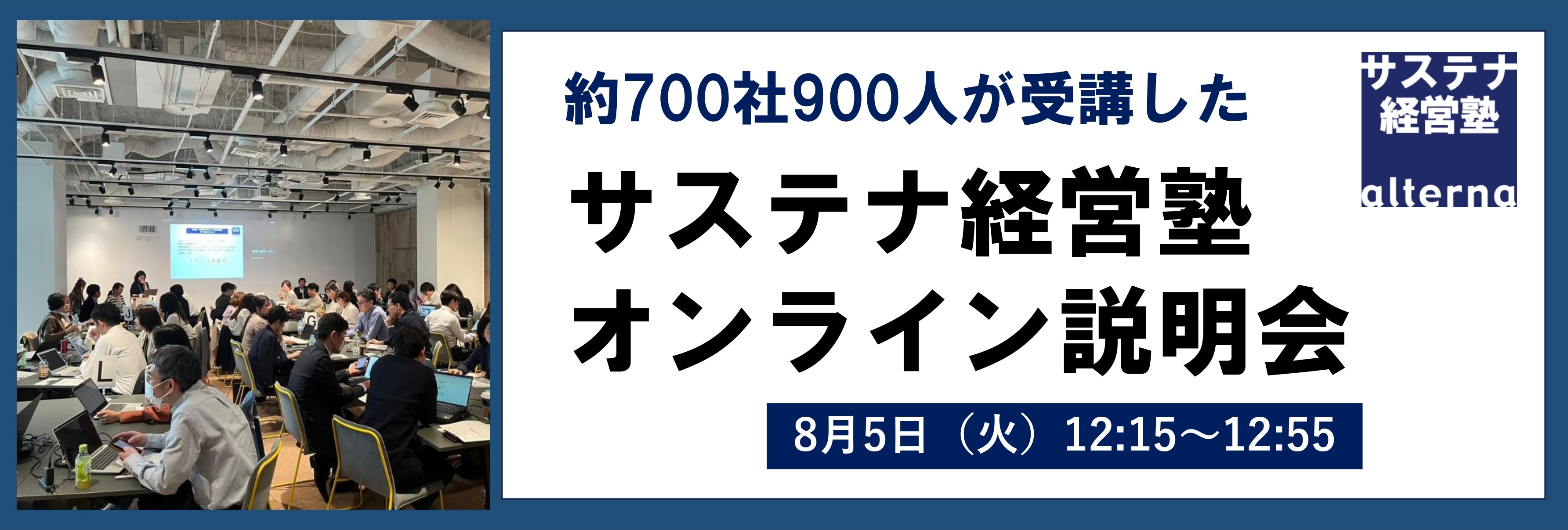




-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)























