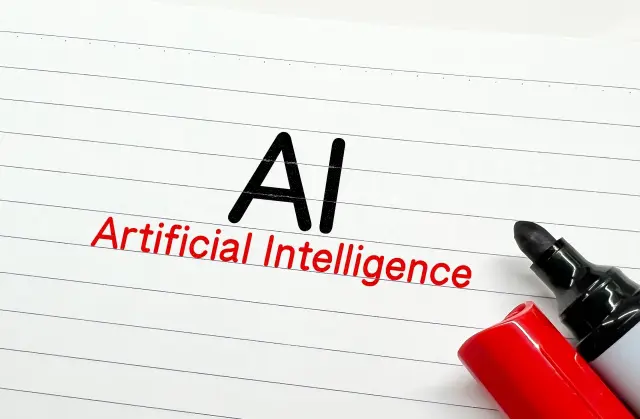いまだに(2022年5月)多くのスーパー店頭で品切れが続くメガヒット商品「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」を開発したのは、ミレニアル世代の中堅技術者だった。グッドデザイン賞を取った「六条麦茶 江戸切子デザインボトル」をデザインしたのも彼だ。その古原徹氏が今年、地域の社会課題を解決したいと上司に直談判し、新しい会社を立ち上げた。(聞き手・オルタナS編集長=池田 真隆)

アサヒグループは今年1月、社会課題の解決やサステナブルな事業に特化した新会社「アサヒユウアス」を設立した。新会社を提案したのは、同社の古原徹・たのしさユニットリーダーだ。他企業と連携するオープンイノベーションでの商品開発や、社会課題の解決を通じてビジネス創出する「SDGsアウトサイド・イン」戦略を聞いた。
主な内容
■「アサヒグループ初のグッドデザイン賞は僕が取ります」
■「みんなビール作りたくて入ったのに、なぜパッケージなのか」
■「飲み終わっても、家に飾っておきたいと思える容器」を
■スーパードライ「生ジョッキ缶」はこうして生まれた
■「サステナビリティに特化した事業部を立ち上げてほしい」と直訴
■パナソニックと「セルロースファイバー」で協働
■「作り手を見せることで共感や応援が生まれる」
■私たちがやるべきことは「買い方を変える売り方」
※参考記事 SDGsの第2ステージは「アウトサイドイン」
■「アサヒグループ初のグッドデザイン賞は僕が取ります」
――古原さんは「生ジョッキ缶」やグッドデザイン賞を取った「六条麦茶 江戸切子デザインボトル」など様々な商品の企画を手掛けてきました。古原さんが社会課題の解決に特化した事業に専念するようになった背景は何でしょうか。
私は島根県松江市で生まれました。漁師の祖父と、公務員の両親のもとで育ちました。松江には高校までいて、大学は東北大学工学部に進学しました。サーフィンとスノーボードサークルを仲間と立ち上げ、朝4時に起きてアウトドアスポーツをしてから授業に行くようなアクティブな学生でした。髪も金髪だったので、理系の中ではかなり目立っていたと思います。
アサヒビールに就職しましたが、そのことも周囲は驚いていました。東北大学工学部からは自動車、電機、重工、電力、インフラ系に進む人が多く、飲料メーカーに行く人はほとんどいません。
就活では自分にしかできない仕事をしたいと思っていて、大学が開いた就活セミナーにある飲料メーカーのOBが登壇して、ペットボトルのパッケージデザインについて熱く語っていました。
この話を聞いた時に「おもしろそう」と思ったのです。エントリーシートには「アサヒグループはまだグッドデザイン賞を取っていないので僕が取ります」と書いて面接を受けました。
■「みんなビール作りたくて入ったのに、なぜパッケージなのか」
――2009年に入社してすぐにアサヒ飲料に出向しましたね。
新入社員は入社して約1年は研修を受けるのが慣習なのですが、ペットボトルのパッケージ開発をやりたいと内定者の段階から強く訴えました。自分で設計することで力が付くと考えていたからです。
でも、アサヒビールに入社してパッケージ開発をやりたいと主張する社員なんていません。みんなビールをつくりたいから入ったのに、なぜパッケージにこだわるのか、周囲からは変人扱いされましたね。
前例のない要望でしたが、運がよくて、たまたまそのときは会社としてペットボトル容器の技術者が不足していて、かつ、工場での容器内製化を進めたいと考えていた時でした。こうして入社して半年経たないうちにアサヒ飲料に出向できました。
――アサヒ飲料では8年間、ペットボトルのデザインと設計を学んだのですね。この経験は今、どのように生きていますか。
パッケージやプラスチックの基礎をゼロから学べたことは貴重な財産になっています。いまは図面を書くことはなくなりましたが、技術者が使う言葉で会話できるのは大きいです。「ものづくりの勘どころ」が分かります。
アサヒ飲料は取り扱っている製品が数多く、働いている人も明るく気さくな人が多かったです。「師匠」と呼べる人が何人もできました。そのうちの一人に言われた言葉は自分のモットーになっています。
それは、「1に自分、2に家族、3・4がなくて、5に仕事」です。これは、どんな仕事がおもしろいですかと質問したときに返ってきた答えです。「自分で考えて、自分で設計し、それで世の中に評価されることが一番うれしい」という師匠の価値観は忘れずに持っています。

■「飲み終わっても、家に飾っておきたいと思える容器」を
――上司にも恵まれて、自分の就きたい職場にも行けました。壁に当たることはありませんでしたか。
当然、課題はたくさんありました。よく「ポジティブ過ぎるとペットボトル容器をつくる仕事には向かない」と言われました。そもそも容器は飲み物を安全に飲むまでの防御機能を持っていれば十分で、チャレンジする必要はないと考えられていました。
だから、現場ではいかに不具合を減らせるか、ネガティブなマインドを持つことを勧められます。
でも、飲み終わるとゴミになることに疑問を覚えました。飲み終わっても、家に飾っておきたいと思える容器もありじゃないかと考え、ガラス細工の作家やデザイナーと組んでデザイン性を追求した奇抜な容器を開発していました。
ですが、最初の頃は、「そんな機能は容器に必要ない」「通常のラインに乗せるのは無理」と否定ばかりされましたが。
――2016年にグッドデザイン賞を取った「六条麦茶 江戸切子デザインボトル」はそうした考えから生まれたのですね。
この「六条麦茶 江戸切子デザインボトル」は伝統工芸士の堀口徹さんと共創しました。最終的に「吉祥紋」4種類のデザインをつくりました。実は生産ラインで同時に4種類の異なるデザインをつくるのはリスクがあり、通常は通りづらい話です。

ですが、その前にいくつかの賞を取っていたので、社内評価が少し上がっていたのと、アサヒ飲料のマーケティング責任者とタッグを組んで話を通しました。
2016年にアサヒ飲料で初めてグッドデザイン賞を取り、パッケージ関係の著名な賞をとると社内外で評価されるようになり、マーケ部門の担当者がよく相談に来るようになりました。
それからも自分が望んだデザインの容器を世の中に出せたのですが、気がかりなことがありました。それは、いくらいい容器ができても販売には直接的につながらないということでした。
そんな悩みを抱えていた時に、アサヒビールから戻ってくるよう辞令が出ました。パッケージング技術研究所という酒類の容器をつくる部署です。戻ったからには、これまでの経験を活かして、売り上げに直結する製品をつくりたいと強く思っていました。
■スーパードライ「生ジョッキ缶」はこうして生まれた









-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)